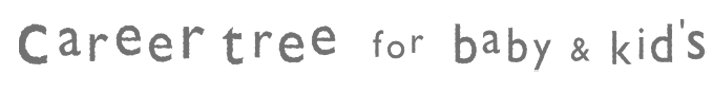共感力を育むには
ひらめきキッズプログラムより

共感力は思いやりにつながる
相手の立場にたって考えられるようになる「共感脳」が発達してくるのが5歳頃になります。
共感脳を育てるには、ファーストステップとして、他の人と自分の考えが違うことを知り、理解することです。
共感脳を育てるのにオススメなのが「Iメッセージ」で伝えることです。
例えば、「お母さんは、最後までお話しを聞いてくれて嬉しかったよ」のようにお母さんが主語で気持ちを伝えることです。
Iメッセージで伝えることによって、自分の発言や行動が人にどんな影響を与え、どんな気持ちにさせるのかということを知ることができるようになっていきます。
絵本の物語を活用しよう
絵本などを通じて登場人物の気持ちを考えたり、どんな気持ちだったのかを自分の言葉で話したりすることで共感力を養うことができます。また、どんな気持ちだったのかをみんなで発表しあうと、お友だちの考えと自分の考えが必ずしも一緒ではないことも知る機会となります。
この時の、関わり方のポイントとしては、「〇〇ちゃんは○○って思ったのね」「〇〇くんは○○って思ったのね」と気持ちを受け止めてあげましょう。気持ちを受け止めてもらう経験を重ねていくことで、相手の話を最後まで聞く姿勢や相手の気持ちを考えて行動するように自然となっていきます。
他者の視点を考える機会を作る
ご家庭でもできる取り組みとして、絵本を読んだ後に「もし〇〇ちゃんだったらどう感じる?」と、話してみたり、ドキュメンタリー番組などを一緒に見ながら疑似体験をすることでも共感力を育むことができます。
ドキュメンタリーのほかに、募金活動も子どもにとって他者の視点を考える機会となります。今世界で自分と同じ年齢の子どもたちがどのような暮らしをしているのかを知る機会にもつながり、多様なバックグラウンドをもった人たちがいることを知り、自分にできることを考えるようになっていきます。
ランドセルを大切に使い、それを寄付しようという気持ちが芽生えたり、玩具の寄付のボックスを見つけると自分から玩具を入れたりする姿が見られるようになったり、そういった視野が広がっていくことで共感力が育まれていくのです。
これからは多様性の時代。多様な人たちとどのようにコミュニケーションをとったらよいのかを考えた時に
共感力はとても大切な力になるのではないでしょうか。